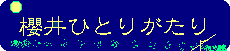-----------------------------------------------------------------------
「たましいのふるさと」
いや、これはまた、いいかたちをしていらっしゃる。で~かっぷはおありでしょうか。
お、おお、また手がぶれた。こうしてレンズ越しにのぞきこんでいても、左の中指が、あなたの先っちょにたわむれかかりたいとだだをこねてしまいます。
この白さ、この円やかさ、どこのどなたか存じあげませんが、ワタシの‘たましいのふるさと’と、およびしてもよろしいでしょうか。おゆるしいただけるなら、すこしは気をおちつけて撮影できそうです。
え、おっけー?
よかったあ、これでまともな絵が撮れる。あつかましいおねがいしてもうしわけありません。じつはつい二週間まえに、美乳じまんのカノジョにだまされたばっかしなんです。いま思いだすだけでも……う、ううう……(といきなり顔を埋めたあとで)――
ちくしょう、こいつのムネも‘ばふっ’て爆ぜやがった!

-----------------------------------------------------------------------
「蒼い時」
なんてタイトルの本があった。
闇が降りてくる一瞬前の空。土曜、人待ちのあいだに気がついた。
この蒼さの遠くには海がある。鋭い三日月の下、鈍色の魚が泳ぐ海がある。味気ない新興住宅地にも、深く、夢幻に沈むときが訪れる。
まもなく人が来た。すっかり濃さを増した宵闇のなか、あたりさわりのないあいさつを交わした。車に乗ったあと、わざとフロントガラス越しに夜空をあおぎ、「ほら、あの雲の横に魚が……」と口ばしってみた。その人はあきらかに怯んだ表情で、運転席に座る僕をうかがった。
「いや、今夜はうまい刺身が食べたいなあ、と思って」
「……そうですか、いきなり魚が出てきて驚きました」
僕はゆるゆると車を進めた。宙を泳ぐ魚群を求め、徐々に西へとアクセルを踏み込んでいった。
のんきに助手席で携帯の着信メールをたしかめる道連れに、真実をいつ切りだせばいいんだろう。‘あなたはここに帰れない、僕とともにあの蒼さの底に没する定めにある’と。